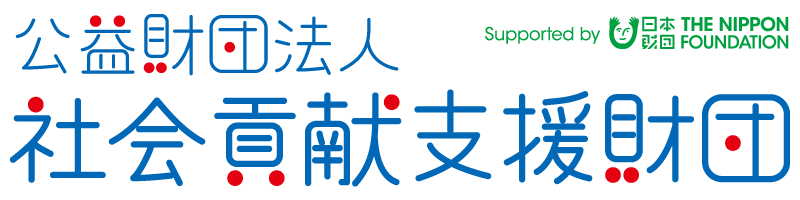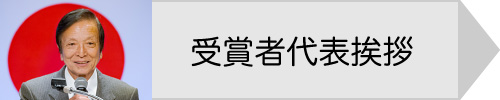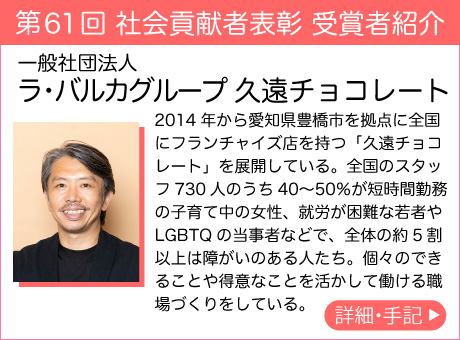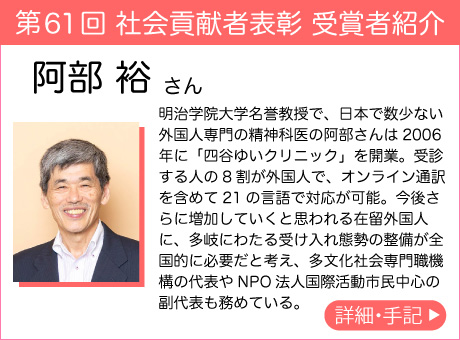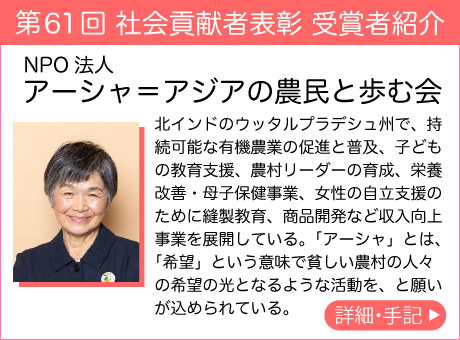第62回 社会貢献者表彰 受賞者一覧
(敬称略)
※ 掲載内容(名称、活動内容、代表者名、肩書き等)は受賞当時のものです。
【功績の内容】
- 精神的・肉体的な著しい労苦、危険、劣悪な状況に耐え、他に尽くされた功績
- 困難な状況の中で黙々と努力し、社会と人間の安寧、幸福のために尽くされた功績
- 先駆性、独自性、模範性などを備えた活動により、社会に尽くされた功績
- 海の安全や環境保全、山や川などの自然環境や絶滅危惧種などの希少動物の保護に尽くされた功績
- 家庭で実子に限らず多くの子どもを養育されている功績
- その他の功績
原田 淑人(神奈川県/フィリピン)
平塚市の小学校教員時代から長くボランティア活動を行い、レバノンやクウェート、オランダなどの海外日本人学校で教えた経験がある原田さんは、フィリピンのシキホール島で、島の子どもたちの教育環境を整えようと2004年から活動している。資金と生活基盤のためリゾートを運営し、インフラの整備や奨学金の支給などを行っている。>> 詳細・手記
推薦者/平塚湘南ロータリークラブ会長 小沢 博
京都市内の福祉施設を福祉ネイリストが訪問し、無償でハンド&ネイルケアを行っている。施術を通じて高齢者や障がいのある人、病気の人などの笑顔が増え、好評なのはもちろんのこと、家族や施設職員にも喜ばれている。また特殊詐欺被害や火災、熱中症の防止を目的に京都府警察や京都市消防局との協働事業も行っている。>> 詳細・手記
推薦者/社会福祉法人 京都市中京区社会福祉協議会 事務局長 藪田 浩司
チャイルドライン ハートコール・えひめ(愛媛県)
18歳までの子どもたちの声を聴く全国的な取り組み「チャイルドライン」の加盟団体として、2001年10月に愛媛県松山市に設立された。毎月5と0のつく日に全国統一フリーダイヤルと子ども電話「ひびき」2回線で電話を受け、誰かに話したいという子どもたちの気持ちを受け止めている。>> 詳細・手記
推薦者/一般社団法人 愛媛県摂食障害支援機構 代表 鈴木 こころ
産婦人科医の鮫島浩二医師が、2013年に全国の産婦人科医に声をかけて設立し、たとえ予期せぬ妊娠をした人でも安心して出産できる環境を整え、生まれてくる赤ちゃんの幸せを第一に、赤ちゃんを望んでいる家族へ託す特別養子縁組に取り組んでいる。現在全国24の医療機関のネットワークと協力・連携している。>> 詳細・手記
推薦者/こどもSOS ほっかいどう 代表 坂本 志麻
NPO法人 つばめの会(東京都)
ミルクを飲んだり離乳食を食べたりすることを非常に嫌がる赤ちゃんの子育てに苦労した山家京子さんの呼びかけに答えたお母さんたちが中心となり2011年に設立された。小食や偏食の子どもを持つ家族に情報交換の場を提供したり、医療者や社会に向けたセミナーの開催を通じて啓発活動を行っている。>> 詳細・手記
推薦者/弘中 祥司
道村 静江(神奈川県)
パソコンの普及によって、視覚障がい者に「漢字変換の知識」が必要となったことで、盲学校の教師だった道村さんは漢字学習のための教材を開発し、点字使用者の漢字習得を可能にした。その後、発達障害や学習障害などの子どものために見て唱えて覚える「ミチムラ式漢字学習法」考案し、子どもたちの学力向上に貢献した。>> 詳細・手記
推薦者/公益財団法人 共用品推進機構 業務部調査研究課 課長 金丸 淳子
下町グリーフサポート響和国(東京都)
20数年にわたり、グリーフケアの研鑽を重ねてきた本郷由美子さんが代表を務める。本郷さんは2001年に「大阪教育大学附属池田小児童殺傷事件」で小学校2年生の娘さんを亡くされた。「心が響き合い、人々がひとつになって支え合うような社会に」という願いをこめて、多様なグリーフに寄り添う活動とともにグリーフケアを広める講演活動や相談業務も行っている。>> 詳細・手記
推薦者/桑島 寛之
世界屈指のヴァイオリニスト五嶋みどりさんが、誰もが等しく音楽の魅力を享受できるよう音楽を通した交流をしようと1992年に設立した団体。学校や病院、高齢者施設、更生施設での訪問コンサートをはじめ、特別支援学校の生徒への楽器指導支援プログラムの実施、アジアの国々で音楽を通じての国際交流プログラムの実施などを行っている。>> 詳細・手記
推薦者/国立病院機構米沢病院 院長 飛田 宗重
社会福祉法人 ゆうかり(鹿児島県)
1967年に鹿児島市に設立された知的障害者支援施設ゆうかり学園を中心に、障がいのある方々への支援を続けている。入所施設からグループホーム等への地域移行をすすめつつ、共生社会を目指すうえでインクルーシブ保育を実践している。30年程前から、家庭裁判所の依頼で少年の保護育成のための補導受託を現在も継続している。>> 詳細・手記
推薦者/更生保護法人 草牟田寮 理事長 深野木 信
京都市に就労支援A型事業所「ワークチャレンジスタイルGOKENDO」を設立し、障がいや課題のある青年たちが自立できるようサポートしている。理事長の松浦一樹さんは、元京都府警の少年課刑事という異色のキャリアの持ち主。運営するグループホームでは青年たちの親代わりとなって、生活面と仕事面の両方を支えている。>> 詳細・手記
推薦者/アロマテラピー クレア 安川 淳子
公益社団法人 沖縄県母子寡婦福祉連合会(沖縄県)
1972年沖縄県に設立され、県唯一の女性相談場所として年間約300もの相談を受けてきた。現在は母子に限らず父子も含め、ひとり親家庭を対象に日常生活支援としてヘルパーの派遣や、就労支援講習会の開催、資格取得のための資金貸付、ひとり親家庭の中高生を対象とする奨学金制度などを行っている。>> 詳細・手記
推薦者/NPO法人 リトルワンズ 代表理事 小川 訓久
一般社団法人 あまね(佐賀県)
2014年に医療的ケア児をはじめ、全ての障がい児を対象に、放課後デイサービス事業を佐賀県小城市に開所した。生涯にわたって障がいのある子どもとその家族に伴走できるよう、2021年には小児科クリニック・医療型短期入所・福祉型短期入所・グループホームを備えた多機能型拠点を全国初の取り組みとして開始した。>> 詳細・手記
推薦者/公益財団法人 笹川保健財団 会長 喜多 悦子
森林塾青水(群馬県)
「飲水思源(水を飲む時は、その源を思うべし)」を合言葉に、群馬県みなかみ町藤原地区「上ノ原茅場」の里山で保全活動を行っている。「上ノ原茅場」は開発を逃れていたものの荒廃して森林化しつつあったが、40年ぶりに「野焼」を復活させ本来の姿を取り戻しつつある。>> 詳細・手記
推薦者/日光茅ボッチの会 代表 飯村 孝文
NGO スリヤールワ スリランカ(愛知県/スリランカ)
1996年からスリランカの、主に子どもたちを対象に様々な支援活動を行ってきた。1998年には農村女性の自立のための職業訓練所を建設。2004年のスマトラ沖地震のあとには、託児所を建設し3、4歳児の幼児教育を始め、子どもだけではなく、親の意識改革にも貢献した。>> 詳細・手記
推薦者/NGO スリヤールワ スリランカ 事務局長 服部 義道
一般社団法人 野のゆり(山形県)
山形県鶴岡市で3人の実子を育てるなか里親登録し、これまでに19人を養育した須藤九二子さんが理事長を務める。養育した里子の中には発達障がい、知的障がいのある子もいて、自立の難しさを経験したことから、ふたつの障がい者グループホームも運営している。3か所目のグループホームの開設も予定(2024年現在)。>> 詳細・手記
推薦者/NPO法人 チームふくしま 理事長 半田 真仁/有限会社 スエヒロ 代表取締役 平形 洋司
NPO法人 いのちのミュージアム(東京都)
殺人事件、交通犯罪、医療過誤、いじめなどの理不尽に生命を奪われた犠牲者が主役のアート展「生命(いのち)のメッセージ展」の企画・運営、相談業務等を行っている。2001年11月28日「危険運転致死傷罪」が刑法に新設されるきっかけとなった署名活動を行った。>> 詳細・手記
推薦者/グリーフサポートやまぐち
NPO法人 親子の未来を支える会(千葉県)
出生前から胎児とその家族のサポートする活動を2015年から行っている。妊婦やその家族を支える「胎児ホットライン」を設置。医療的ケア児の支援や、患者家族やグリーフケアに関わる医療者の交流会、勉強会の開催、出産前から使えるオンラインピアサポートシステムの運営などを行っている。>> 詳細・手記
推薦者/公益財団法人 日本ダウン症協会 代表理事 玉井 浩
一般社団法人 OPEN JAPAN(宮城県)
1995年の阪神淡路大震災時に設立された民間の非営利団体「神戸元気村」に関わったメンバーを中心に「ボランティア支援ベース絆」として東日本大震災発生時に宮城県石巻市で活動を始めた。2012年に一般社団法人となり、これまでに37の災害現場で緊急災害支援活動を行ってきた。各被災地にいち早く駆け付け、徹底した現場主義で被災地のニーズに応えている。>> 詳細・手記
NPO法人 市民ひろば なら小草(奈良県)
奈良市立春日中学校夜間学級に勤めていた教員有志が、在日外国人のために始めた学習会が形を変え、2015年に無料学習塾を始めた。その後、不登校児童のための無料フリースクール、高校生の居場所、18歳以上の若者の居場所の開設、通信制高校の開校するなど、すべての子どもたちが自分らしく生きていける道を見つけられるよう手厚いサポートを続けている。>> 詳細・手記
推薦者/架け橋 長島・奈良を結ぶ会 会長 稲葉 耕一
NPO法人 つなげる(兵庫県)
双子や三つ子など多胎家庭の支援や多胎育児に特化した活動を中原美智子さんを中心に2011年から行っている。同じ境遇の仲間とつながることができるオンラインコミュニティの運営や実際に会って話せる場所づくり、多胎育児のスキルを伝える情報コンテンツ配信などを行っている。>> 詳細・手記
推薦者/認定NPO法人 女性と子ども支援センター ウィメンズネット・こうべ
地域活動支援センター 北九州マック(福岡県)
依存症者の日中の居場所がなかった北九州市地区に2012年6月に開設された。アルコール、ギャンブル、ゲームの依存症者や、近年では受け入れる医療機関が少ない触法依存症者(薬物、窃盗、性嗜好)といった、多様化するすべての依存症からの回復と成長を目指す支援に取り組んでいる。>> 詳細・手記
推薦者/特定非営利活動法人ジャパンマック 代表理事 岡田 昌之
一般社団法人 障がい者アート協会(埼玉県)
障がい者の生み出すアート作品をオンラインギャラリーでの公開を通じて社会に周知しながら、その作品や創作活動の対価を創作者本人に還元できるよう2015年から取り組んでいる。現在、1,700人の登録者の5万7,000件を超える作品が公開されている。昨年度は64の企業や団体の事業活動にこれらの作品が活用された。>> 詳細・手記
推薦者/公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を 代表理事 大住 力
NPO法人 子育て応援レストラン(大分県)
ひとり親、障がいのある子を育てる世帯、困窮する子育て世帯に特化し支援しようと、若林優子さんを中心に子ども食堂の運営と食材や日用品などの配布を2017年から大分市内で始めた。また地域の人と人を結びつける「地域共生型農園」の運営し、農作業を通じた地域づくり活動も行っている。>> 詳細・手記
推薦者/大分市教育センター 上野 真
1965年に発足し、心臓病の子どもについて、高額な治療費の無償化、心臓健診の実施などを行政に要望し実現してきた。また幼稚園などへの入園が難しい子どもたちのために1975年に開設した自主保育の場「パンダ園」は、子どもの社会性を育むだけではなく、保護者同士の交流や情報交換の場として設立50年を迎えた。>> 詳細・手記
推薦者/認定NPO法人 心臓病の子どもを守る京都父母の会 理事 余田 由香利
(学校法人 同志社 評議員 学校法人 マクリン幼稚園 理事)
(学校法人 同志社 評議員 学校法人 マクリン幼稚園 理事)
NPO法人 ユニカセ・ジャパン(東京都/フィリピン)
フィリピンと日本で青少年育成事業を行っている。フィリピンでは、貧困による負の連鎖から子どもたちが抜け出せるよう、ビジネストレーニングと食育事業を展開し、日本国内では国際協力やソーシャルビジネス、グローバルキャリアデザインなどに関心のある人に向けた講演会や年に一度「アジアカンファレンス」を主催している。>> 詳細・手記
推薦者/Primer Media, Inc. Japanese Client Sales Supervisor 茨木 國光
市川 晋一(秋田県)
山手線内4倍の面積に人口4,000人の秋田県仙北市西木町でたった一人の医師として、地域医療を担ってきた。移動手段を持たない高齢者のためにオンライン診察ができる移動診療車両を県内でいち早く導入し、365日24時間体制で住民の健康を支えている。>> 詳細・手記
推薦者/佐々木 正光
鳥海山にブナを植える会(秋田県)
1994年から秋田県の鳥海山3合目・霊峰公園付近でブナの植樹を続けている。かつてブナを伐採して植えられたスギやカラマツなどの人工林が放置され、きれいな水や森林の保水力が低下していることを危惧した地元の有志たちが始めた。「100年続けよう」を合言葉に鳥海山の自然を守るこの活動は今年で30周年を迎えた。>> 詳細・手記
推薦者/佐々木 正光
VO ひまわり(福岡県)
ひとりで外出することが困難だったり不安がある人などの外出支援を福岡市で2011年から行っている。利用者は高齢者のみならず、車いすの利用者や認知症、障がい者のある人など、子どもから大人まで様々。「映画館で好きな映画見たい」「同窓会に出席したい」「初詣に行きたい」など、行先も多岐にわたっている。>> 詳細・手記
推薦者/社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会 ボランティアセンター 所長 小山 浩俊
NPO法人 おおむら里山村づくり委員会(長崎県)
“使われない公有地を使える共有地にしよう”をスローガンに街なかにも近い、広大な長崎県大村市の徳泉川内の旧実習地で繰り広げられているワークショップ方式の環境保全活動とその環境を生かした子どもの冒険遊び場づくりのプレーパーク等、多世代のための居場所づくりを進めている。>> 詳細・手記
推薦者/大村市 大村市長職務代理者 大村市副市長 山下 健一郎
NPO法人 どうぶつたちの病院 沖縄(沖縄県)
沖縄県で、琉球弧に生息する希少な野生動物を守る活動を行っている。ヤンバルクイナやイリオモテヤマネコなどの希少種をはじめ沖縄の豊かな生態系を次世代に継承するため、行政や研究機関とも連携しながら、傷病救護、交通事故対策、外来種対策だけでなく、希少種の死因検索、保全策の提言、救護体制の構築、遺伝資源保存、野生復帰技術開発にも取り組んでいる。>> 詳細・手記