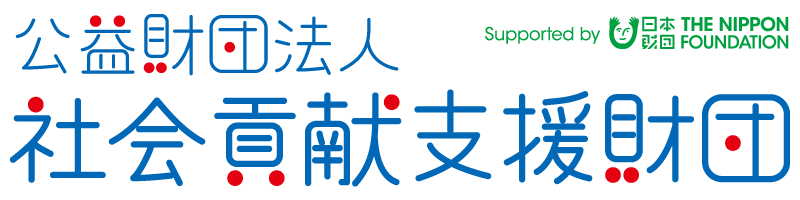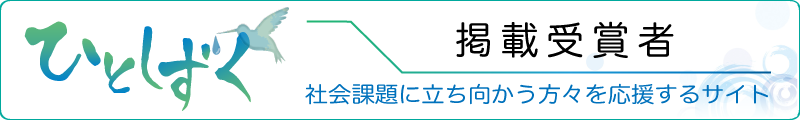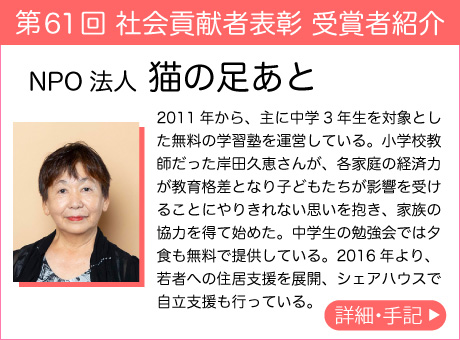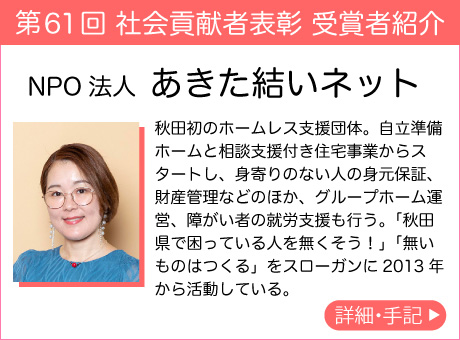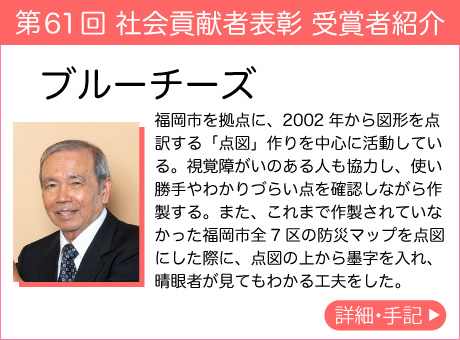NPO法人 つばめの会

摂食嚥下に問題がある、経管栄養を使用している、小食や偏食で成長発達に影響が出る摂食嚥下障がい児の保護者に向けて、情報交換の場の提供、受診可能な医療機関の紹介、医療従事者や社会への啓発活動を2011年から行っている。食べて飲み込むことは生来備わっている機能と思われがちだが、哺乳、離乳食、幼児食と段階を経て学習する機能であり、様々な消化器官が連携して行われる。その学習過程で疾患など何らかの理由で、一部や全てが正しく機能しない状態を摂食嚥下障がいと呼ぶ。代表を務める山家京子さんは、摂食嚥下障がいのある我が子のことを小児科医に何度も相談するも「赤ちゃんは吐くもの。体が大きくなれば吐かなくなる」「与え方が悪い」などと授乳方法や与えるときの表情の問題とされてしまい、不安で辛い日々を過ごし追い詰められた。その経験をブログに綴ると、反応があり同じ経験をしている人たちがいることがわかった。必死で食べさせることが虐待なのではないかと悩む人や食べることを嫌がる幼い我が子との関係が複雑化してしまう人、鼻から胃に通したチューブから栄養を入れる経管栄養がいつ外せるのか悩んでいる人もいる。小児科医にも摂食嚥下障がいのある子の存在が殆ど知られていなかったことや医療的な対処が確立されていないことを問題と感じ2011年から活動を開始。メーリングリストで会員同士の情報交換をはじめ、専門家から学ぶ勉強会や交流会の開催、医学会でのブース出展、医療や福祉関係者に向けのセミナーの実施に力を入れている。
つばめの会は2011年に摂食嚥下障害児の親の会として設立されました。当初3名の親で設立した団体ですが、現在は入会者数が400名を超え、毎月一定数の入会希望者より連絡が入ります。主に情報を求めて検索して入会する会員が多く、家庭で対処するための情報は十分に行き届いていないといえます。
対象となる子どもは、経管栄養児、拒食(思春期痩せ症と考えられるものは対象外)、経管栄養依存症、極端な偏食少食がある乳幼児です。特定の疾患ではなく「飲食に困っている子どもの家族」という枠組みで活動してきました。
活動は主に2方向で、1つは患者家族にむけた活動、もう1つは医療者や支援職の方にむけた活動です。
患者家族に向けては、患者家族が摂食嚥下に困難のある子どものケアをするにあたり必要な情報をやり取りする場を作る活動を行っています。医療的ケアや持病により外出が難しい子どもも多いため、メーリングリストでの相談やオンラインのおしゃべり会を中心にピアサポートを行っています。
医療者や支援職に向けては、このような子どもの診察・支援をよりスムーズに実施していただくため、主に医学・歯学系の学会において啓発活動を行っています。これはこの症状の子どもの受診先が日本国内で少なすぎて保護者が困っているためです。この症状を相談できる医療施設を増やすことを目的として10年以上続けております。当初は学会でも素通りされる患者団体でしたが、現在は情報を集める医療者の方が増えています。ついに令和6年には、医療者・支援者向けのセミナーを4回連続コースとして実施することができました。セミナー参加者からは長期的に継続した受講を希望する受講者が多く、令和7年度から新たな形で医療者・支援者が学び続けることが可能になるよう準備を進めています。
いずれの活動もスタッフのボランティアだけでなく啓発資金が必要で、特に啓発活動は資金がなければ実施が難しいのが現状です。全国の困った子どもの受診先を作るため重要ですが、そのためには医療者が学べる体制作りが重要となります。今回、表彰をいただいたおかげで来年度からの研究会の設立に向け、準備を進められるようになると考えています。手弁当で活動を続ける当会には非常にありがたく、将来の患者家族の未来へ大きく貢献できるきっかけとなります。活用できるよう引き続き努力いたします。改めてありがとうございました。