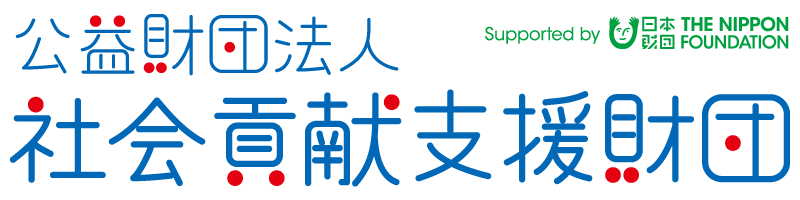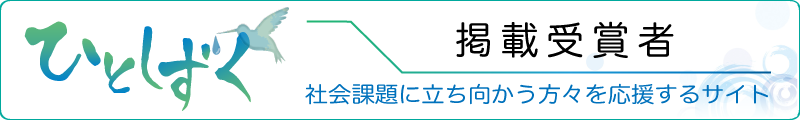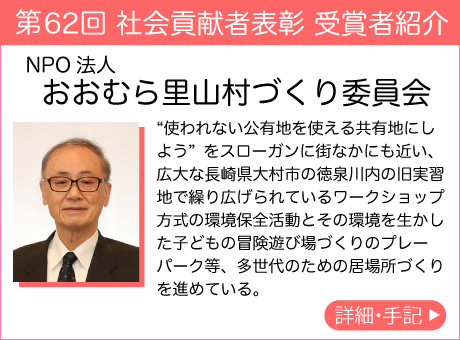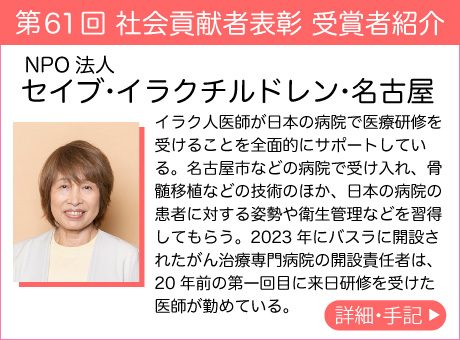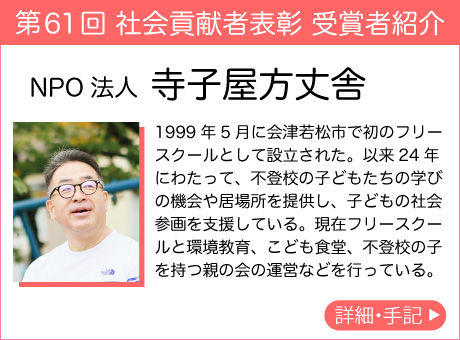NGO スリヤールワ スリランカ

「いつか子どもたちに教育の機会を、貧困から脱却するには教育しかない」服部和子さんは、1982年にはじめての海外旅行で訪れたマレーシアで、子どもたちが学校にも行かず物売りをしている光景に衝撃を受けた。国際交流活動を続ける中、1996年にUNCRDから開発途上国派遣員としてスリランカを訪問し、サンフランシスコ講和会議(1951)で対日賠償請求権を放棄する演説を行った、J.R ジャヤワルダナ元大統領(当時財務大臣)に面会の機会を得た際 “I am very happy to meet many wonderful Japanese people in my life.”と、スリランカに対する取り組み、想いに大変喜ばれた。現地から「子どもたちが野球をやりたくても用具がない」と聞き、帰国後直ちにスリヤールワ スリランカを設立し、中古の野球用具を集め、畳み2畳分の木箱で送った。翌1997年にはスラムエジアに職業訓練所を開所。1998年には日本企業の協力を得て、工業用を含め400台以上のミシンを寄贈し、農村女性の自立のための職業訓練所を建設、運営。その後、2004年に起きたスマトラ沖地震による津波で甚大な被害を被ったスラムエリアに、支援物資を送るとともに、親が安心して働ける環境をと、翌年には日本のボランティア貯金を活用して託児所を建設。3、4歳児の幼児教育をスタートさせた。貧困家庭の子どもからは授業料(月額日本円で500円)を免除している。国内では講演をはじめ、各種イベントに参加して、スリランカの現状を伝え、理解を得るように努めている。
みなさまの温かいご協力のお蔭で「人生最大のご褒美」をいただけたことに深く感謝申し上げます。
1996年UNCRDから開発途上国派遣員としてスリランカを訪問。三都市の市長、NGOとの懇談会、スラムエリアの視察。この時、現地から「野球をやりたくても野球用具がない」と支援要請。子どもたちの夢を叶えるため、帰国後直ちに「NGO スリヤールワ スリランカ」を設立。
1998年「女性の自立のための職業訓練所」は足踏み式ミシン、その後は本格的に工業用ミシンを導入。ローカルマーケットからの受注は訓練生たちの家族、唯一の現金収入に結び付いた。
2004年12月26日に起きたスマトラ沖地震津波。スラムエリアに住む約400人が避難したお寺に、トラックを含む車4台。荷台には「Sri Yaluva Sri Lanka Japan」の横断幕。職業訓練所の訓練生が作った下着や衣類に加えて、米、紅茶、砂糖、歯磨きセット等、袋に詰めてひとりひとりに手渡し。「日本からのお金であってもスリランカの人を直接助けることを誇りに思う」と話す訓練生。1月現地入り。「face to face」顔の見える支援をみな待っていた。津波被災者支援のあと、復興支援として親が安心して働けるようにと託児所を建設。子どもたちのため、スリランカの未来のために3、4歳児の幼児教育をスタートさせた。食べるものを食べ、自分の人生は自分で選択できるように、貧困から脱却するには教育が重要だと、開発途上国訪問の都度、感じてきたことだ。
子どもたちの笑顔に癒されつつ、自立運営を目指してきたが、コロナ禍、経済危機が、それを難しくした。日本、スリランカ双方の努力だけでは、乗り越えられない経済的大きな壁が立ちはだかる。ボランティアにかかわったおかげで、多くの貴重な体験を積み重ねることが出来、いつしか私の「ライフワーク」となり、充実した日々に感謝。スリランカから心が離れることはない。
今後の展望は、前名古屋市長の河村たかし氏から「スリランカとの友好提案書」を書いてくださいとのアドバイスもあり、スリランカの託児所(幼稚園)と名古屋の大学に付属する幼稚園の先生との交流の機会を作りたい。また、30年近く続いた内戦のなかから生まれた世界平和を願っての美しい曲「ロエ サマ」をみなさんと踊りたい。