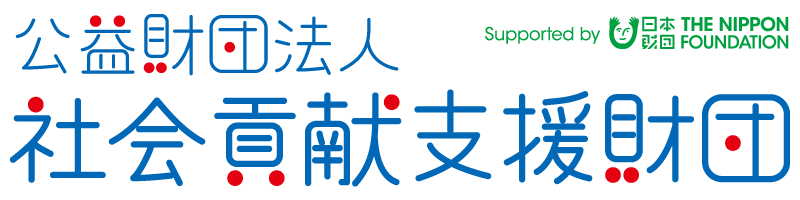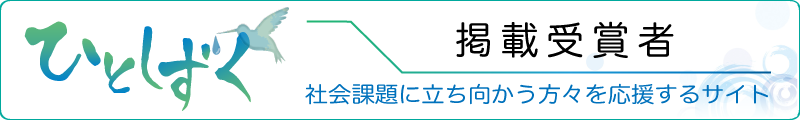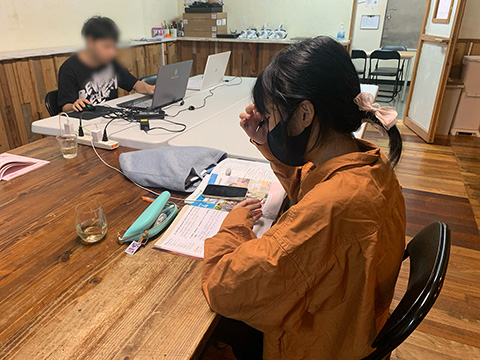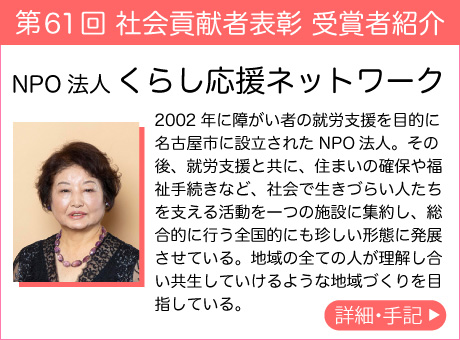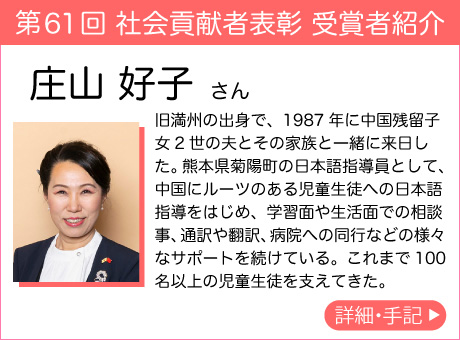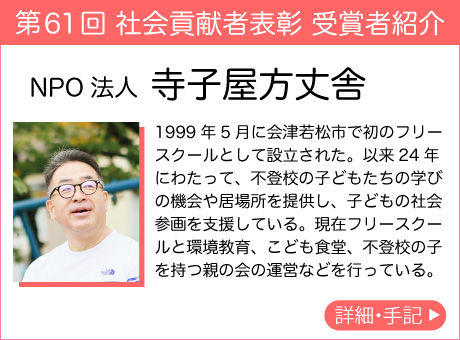NPO法人 沖縄青少年自立援助センター ちゅらゆい

子どもの相対的貧困率が29.9パーセント、3人に1人は貧困と全国でも最下位である沖縄県で、不登校やひきこもり、障がいなどが理由で社会的に孤立している子ども、若者たちへの支援を目的として2010年に設立。生活保護や経済的困窮など、家庭力が弱い子どもたちにアプローチ、子どもたちの「やりたい気持ち」を大切に、安心できる居場所を提供している。那覇市で10歳から20代前半の子どもの居場所「kukulu」、うるま市で障がいのある18歳以上の人を対象にした就労移行継続B型支援「コミュっと!」また、うるま市立田場小学校に通学する小学1年生.3年生までの帰宅後に保育を必要とする子どもたちの居場所「b&gからふる田場」を運営している。また、夜間こそ危険に巻き込まれたり、孤独感や不安感が増したりする可能性が高いことから、15歳.39歳までが気軽に利用できる夜の居場所「ユースセンター・アシタネ」を2023年春にオープン。特別なケアはなく、若者が主体的にやりたいことに取り組める場になっている。設立から14年、様々な困難を抱える子どもや若者が、ありのままに生きていける社会の実現に尽力している。
ちゅらゆいは、ひきこもりや無業状態の若者の社会参加を応援することを目的に、2007年、有志によって発足した団体です。私はそれまで大阪で若者支援に携わっていましたが、この分野には国の特別な制度がないため、利用料や寄付で運営費を賄ってきました。その後、沖縄に戻ってちゅらゆいを立ち上げるわけですが、大阪とは経済状況が異なり、利用料をいただくことはままなりません。そこで2010年にNPO法人格を取得、家庭の経済的負担を軽減のため、障害福祉制度を活用した運営を始めました。
2013年には那覇市に政策提言し、要保護・準要保護世帯で不登校状態にある中高生を対象とした「子どもの居場所kukulu」を開所しました。ここに通う子どもたちの環境・状況は深刻で、本人はもちろんご家族の多くは孤立状態にあります。(「居場所をください〜沖縄kukuluの子どもたち」(世界書院)をお読みください)
困難を抱えた子ども若者は、必ずSOSを出します。しかしそれは「助けて」というわかりやすい言葉ではありません。彼らは不登校、ひきこもり、非行、無気力など、様々な態度で訴えるのです。しかしそれらは問題行動として扱われるため、怒られ指導を受けた子どもや若者は心を閉ざします。ですからちゅらゆいでは、まず彼らをそのまま受け入れ、安心・安全を提供し、やがて元気になり将来に希望を感じ始めたら、それを全力で応援する。それが我々のスタイルです。
みんなが大好きになってくれたkukuluですが、国の制度変更のため事業廃止になったことがあります。その事実を子どもたちに伝えると、彼らは「仕方ないね」と笑うのです。子どもたちはあまりにも「奪われること」に慣れている。そんな悲しい笑顔を前に、我々は自力で活動を継続することを決意し、寄付を募りながら居場所を作り続けました。
その後、「沖縄県こどもの貧困実態調査」によって、県内の子どもの貧困率29.9%という数字が公表されます。それを機にkukuluは行政の委託事業として活動を再開、現在も子ども若者をとりまく社会課題の啓発を続けています。
ちゅらゆいの次なるテーマは「子ども若者の声を社会に届ける」こと。困難を抱えた子ども若者は、助けられてばかりの存在ではない。彼らの経験や体験にこそ価値があり、一緒に声を上げ、社会を変えるパートナーであると、我々は信じています。
今回の受賞を励みに、今後も「全ての人の尊厳が守られ、認められる社会」を目指し、子ども若者と共に歩み続けます。